まえがき
この書きものは私が見、聞き、経験したことをもとに書いた。そのため私的な面が出てくるの
で私という字を加えた。物事には表と裏がある。表だけを知ったのでは全体を知ったことにな
らない。その上伏せておいた方がよいと思う裏話でも明るみに出した方が、通り一遍の事実に
陰影を与える方に働き、それを傷付ける方に働くことは少ない。特に過去の古いことにおいて
はである。私は以前、外国の科学雑誌でニュートンのリンゴの話を読んだことがある。確かに
ニュートン家にはリンゴの木があったが、あの話はニュートンの甥のConduitという男が金儲け
のために考えた作り話であるというのである。これが本当かどうかわからないがニュートンを
傷つけることにはならない。むしろニュートンへの関心を甦らせることになるのである。
以前九大の生理学教室に高木健太郎という人がいた。この人が薬学の元老下山順一郎先生
の息子であることを知る人は少ない。ただ、その後名大学長になり、参議院議員になった人で
あるということで終わる。知ることでこの人の存在が身近なものになるのである。
以上二つの例が示すことがこの文を書くについての私のスタンスである。
明治四十五年:
話はここから始まる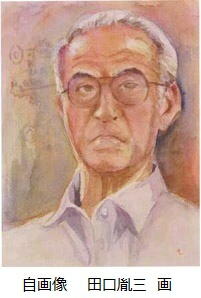
私は製糸会社の息子として生まれた。それは明治四十五
年であったから、この話はそのころから始まる。製糸には副
産物として蛹(サナギ)が出るがその利用法が問題になって
いた。たまたま父は郷里から頼まれて酒井某という薬学専門
学校出身者をあづかることにしたが、この人物にこの問題の
開発の仕事を与えた。会社ではぶらぶらしていたが、秘かに
これを京大の生技研(?)に持ち込み蛹をアミノ酸に分解す
ることを試み、それを飲料にする個人特許を得た。そしてそ
れを武田薬品に売り込み、大五製薬という別会社(武田栄養
の前身)を作って、「ポリタミン」というアミノ酸飲料を売り出し
た。当時は結核患者が多く、その栄養剤として用いられ、そ
の販路を拡げた。これが今のドリンク剤の祖と言えないこともない。私も飲んでみたが、臭くて
健康では飲むに耐えられるしろものではなかった。その後この原料は牛乳のカゼインに代わ
った。私はこういうことに触発されて薬学に進んだのではない。高校の時薬学には朝比奈泰
彦という有機化学の大家が居られることを知り、薬学に進んだのである。当時の大学はどん
なふうであったか。
東京帝國大学薬学科に入る
入試
私の場合を例にして話すと、入試は外国語、物理、化学で行われた。物理はα、β、γ線
の問題、化学はSaurenitrilの反応が出た。高校では化合物名は英語と独語で習ったが、ゾイ
レニトリルなんという化合物は聞いたことがない。それでニトリルの反応に全部COを付けて書
いた(言うまでもなく、これではケトニトリルだ)。試験が終わろうとする頃、一受験生が「ゾイレ
ニトリルとはニトリルのことですか」と聞いたら、試験官が頭を縦に振った(これは許されない
行為だ)。それで周章ててニトリルに付けたCOを全部消した。これがなければ今の私はなく、
他のものになっていたであろう。試験後面接があった。これには慶松先生(薬学科長。あとに
出てくる)と緒方先生(緒方知三郎の弟。ホルモン化学)が立会った。「兄弟は何人か」と聞か
れたので私を除いた人数を答えた。そしたら緒方先生が書類と違うと問い返してきた。まずっ
たなとどきどきしていたら慶松先生が「それでいいんだ」と私に同意し、両先生の間で口論にな
った。試問される私は蚊帳の外でそれを眺めているうちに終わってしまった。これら一連の入
試のありさまを経験して私は大学とは案外居心地のよいところになるなと感じた。
当時の薬学教育
大学の教育はケキュレに倣って試験よりも実験が重ぜられた。従って試験の時はどんな本
を持ち込んでもいいというのもあった。しかしその場になって監督の助手が「いかん」ということ
もあって戸惑うこともあるにはあった。柴田桂太先生(植物生理学)などは答案が八枚以上に
なると読むのが面倒だから通すという流説もあったので、大きな字で八枚以上書いた。また高
木誠司先生(分析)は教室へ来てわれわれが身を寄せ合って書いているのを見て「隣の答案
と間違えないでくれ」と言って去った。この皮肉には一本も二本も参った。
講義の方のことを言うと、皆大切であろうが面白くないものもあった。その代表的のものが当
時の衛生化学であった。そのため出席者が二、三名のこともあった。思い余って担当の服部
先生が私のところに来て「皆何故出ないのか」と不満をぶちまけた。私は「先生の講義は毎年
全く同じだから代々ノートが受け継がれ、それで済ませているからです」と答えたら、先生は散
切り頭をかきながら「俺だって少しは変えているぞ」と少し照れ笑いを浮かべながら私を見た。
私は先生の立場にある人のこの純真そのものの飾らぬ仕草を目にして心から感動し、先生
が好きになり、皆を誘って講義に出席することにした。これはお義理にしたことではなく、話を
聞くということはその人の人柄にも触れることでもあると気付いたからである。
薬学の近代化
長井長義先生と丹波敬三先生
話は少し逆戻りするが、薬学を近代化されたのはわれわれの先生の一代前の先生がたで
ある。その代表的な先生が長井長義先生である。先生はドイツ留学より帰国されてその職に
つかれた。大学へは一頭引きの馬車で通勤されたが、本郷の石畳の上を走る馬車のパカパ
カという音が今尚聞こえるような気がする。先生は日本女子大の方も兼任されており、そちら
の方の講義には欠かさず行かれるが、薬学の方では時間になっても教室へ来られないので
学生が引っ張り出しに行ったという話も聞いた。また過日テレビで俳優の丹波哲郎が「わしは
じじが新宿に広大な土地を残してくれたから金には困らぬ」と嘯いているのを聞いた。このじじ
とは長井先生と並ぶ丹波敬三先生のことである。先生は国産のサルバルサンを作りタンバル
サンと名付けて売り出した。当時はカサ(梅毒)気のない者はないと言われた程この病気は蔓
延していたから、その売行きは凄さまじく先生は巨万の富を得たのである。哲郎の言うのはこ
れである。因みにサルバルサンとはご承知のように有機砒素化合物であるが極めて不安定で
精製ができない。そのため合成の慣れが物を言い、熟練者が作ったものを唯マウスの毒性試
験にかけ基準にあったものを市場に出していたのである。極めていい加減と言えばいい加減
であるが、他に代わるものもなく梅毒の恐ろしさがそれを許していたのである。
朝比奈蕾軒先生と牧野富太郎先生
どの時代でもそうだが、学生はいたずら好きで、スキャンダラスな話を好む。あの先生は二
号があるとか、内科の某教授は婦長が代わるごとに自室でやっつけてしまうとか、どこまで本
当かわからぬが、火のないところに煙は立たぬと言うことが学生に通用するかどうか。またこ
んなことも聞いた。医学部では法医解剖がある。学生も教育のためそれに立ち会う。事件の
対象が若い女性の場合は薬学の連中も出掛ける。白い実験衣を着ていけばフリーパスであ
る(私は行っていない。本当だ)。時には教授に質問されて化けの皮が現れそうになったことも
あったそうだ。話は飛ぶが、三年の時の私の実験室が朝比奈先生の居室の隣にあった。そ
のため先生の部屋へ出入りする人物を見ることができた。その中で派手な格子縞の洋服を身
につけ馬が顔負けするような長い顔をした人がよく出入りするのを見掛けた。これが牧野富太
郎先生であった。先生は植物学の泰斗であったが理学部では講師止まりであった。朝比奈先
生は肩書きなどを問題にする人でなく、学識を重んぜられたから、牧野先生の最高の理解者
であり友人でもあった。この牧野先生が切通し(地名)の待合いから通っているという噂が学
生の間で流れた。こんなこともあって牧野先生は講師止まりであるのだなとわれわれは思っ
た。近年になって私はこの噂が事実であり、その夫人が待合いを経営されていたことを知っ
た。植物採集(遊びを含めて?)出費が嵩むのを埋め合わせるための夫人の思い余っての策
であった。正に近代の山内一豊の妻である。
当時の教室
朝比奈研究室
私は朝比奈先生の弟子であるから、その教室をモデルに当時の教室の様子を話しておく。
先生は恩情の篤い方であったが、研究・実験は極めて厳しかった。先生は化学者であった
が、成分で植物を分類するケモタキソノミーの道を開いた植物学者でもあったので、自から蕾
軒と号したが、弟子共は草冠りをとって雷軒と呼んだ。雷軒ぶりを示すと、昼食なども食堂へ
食べに行くなどはもっての外で、いつ食べるともなく食べなくてはならぬのである。この雷軒先
生も時には出張される。その時が教室の春である。その時は学生の方からではなく教室員の
方から「野球をやろうではないか」と声が掛かる。雷軒先生は知らぬが佛で、こうして教室の硬
軟のバランスがとられていくのであった。先生は植物成分の構造研究オンリーであったが、あ
る時先生に薬理の田村教授から強心剤「カンファー」の話が持ち込まれた。カンファーを与え
ると体内で変化した後、初めて強心作用を示すが、どう変化するのかという問題である。朝比
奈先生ははじめ余り乗り気ではなかったようであったが、テルペン化学に発展することを期待
して引き受けることにした。そして体内でπ(パイ)の位置(当時の命名)が酸化されることをつ
きとめた。しかしその位置だけを化学的に酸化することは難しく、武田薬品の工場で犬にカン
ファーを食わせ、その尿から取り出す方法をとった。犬は大変興奮し、吠え立てるので近所か
らひどく苦情が出たという話だ。その後化学的に酸化することに成功し、ビタカンファーとして
発売され広く用いられた。その特許料が入るため朝比奈教室は大変裕福になり、副手達も月
五〇円(当時の助手の給料は七〇円)もらっていた。この薬は臨終の際にもほとんど用いられ
た。私も母の場合に経験したが、知り合いのお医者さんが来て、この薬を打つと間髪を入れ
ず「御臨終です」と頭を下げた。薬のことだから打ってから少しは様子を見ての後と思いこんで
いたのに、これでは全くのセレモニーで、それ以来私はこの薬を臨終薬と名付けた。ビタカン
ファーに遅れること暫くして理研関連の会社からカンファーの他の位置が酸化されたものが強
心剤カンフェロールとして売り出された。これは鈴木梅太郎先生の指導によるもので、これが
もとで両先生の間に水がさされた。この論争は泥仕合として新聞の三面記事に大きく報道さ
れたが、これらすべてカンファーに関する話は過去のものとなった。
私の実験
私も三年生の時、カンファーに関連してテルペンの仕事をした。テレピン油によく乾燥した塩
酸ガスを通じるとボルニルクロライドが十数時間の後沈澱してくる。テレピン油の産地によって
は沈澱しないものがあった(当時の技術では沈澱しないと分離できなかった)。ところが輸入元
で小分けするものがわれわれの手元に入るのでどこのものかわからぬ。この話を先生にする
と「旋光度を測ったか」と問われた。私は「テレピン油はテルペンの混ざりだから測っても無駄
では」と答えたら「そんなことでは駄目だ」と理由も言わずに一喝された。何故、先生はこんな
無茶なことを言うかと頭にきたが、一夜考えてみた。そしてこういうことに気付いた。テレピン
油は産地によって組成が違うが、それぞれ大体一定の組成をもっている。そのため旋光度を
測ってみればどこの産地のものか見当がつくと理解できた。理由を言って怒るのではなく、理
由を言わずに当人に考えさせる先生の怒り方に癪にさわったが教えられた。やはり先生は偉
かった。
私はこの頃先生の学者としての日常を覗き見ることができたが、それは凄さまじいと言える程
のものだった。全くわれわれが入れる世界には見えなかった。これでは先生に及ばないまで
も、この道に進む希望すら失ってしまうので私は先生にも少しはわれわれと同じところはない
かと、先生の人間的研究を始めた。幸いにして先生の退職後、一層先生に近付くことができ
て、われわれと同じ凡俗な楽しみのあることを知ることができて安堵した。以来私は学生に偉
い人の話をする時その人の人間的な面、場合によっては欠点も話すようにしてきた。ひとは私
にひとを貶す悪い癖があると思っているかもしれないが、私の真意は前記のようなところにあ
るのである。
朝比奈先生のちょっとしたエピソード
ここでご愛嬌までにちょっとした先生のエピソードを挿入しておく。私は戦後大学に戻った時
に先生(すでに退職)の机を頂戴した。何も入っていなかったが、、一枚のきりりとした美人の
見合い寫真が出てきた。大分時はたっていたが、呉建教授(九大にもいた)の娘さんのもので
あった。受け取って引き出しに収めぱなしにしていた先生も先生だが、この先生に頼む人も頼
む人だと私は笑った。
薬学系で文化勲章を受けた人は四人位いる。その最初の受章者が先生であるが、その話は
他に譲る。昭和十五年に先生はドイツ化学会からその総会で特別講演をするよう招聘された
が、それはわれわれのグローバル化された時代の外国での講演とは訳が違う。特にドイツ化
学会は世界を代表する学会であって、ごく僅かの選ばれた人に依頼が出る。従ってこの講演
者にはノーベル賞の噂が附随する。しかし時は既に第二次世界大戦に入っており欧州の戦雲
が怪しくなった時で、果たして無事帰国できる保障も無いので中止になった。当時欧州を往復
するにはシベリア鉄道によるか、海路によらなくてはならないが、片道約一ヶ月を要した。かく
してすべては水の泡と消えた。
慶松勝左ヱ門先生
同じ頃異色の教授として、薬学士で満鉄中央研究所の所長を勤めた後着任した慶松勝左
ヱ門先生がいた。そこではオイルシェールの研究をされたから、講義もその話が延々と続い
た。何故に薬学でこんな話をされるのかと疑問をもったこともあるが、薬は作用によってその
名が付くのであってオイルシェールも物であることに変りはないから、それを取り扱う技術には
共通のものがあるし、応用を広めることにもなると解して納得した。
化学工業畑で活躍した私の友人たち
当時の薬学はこういう理解のもとに教育が行われたように思う。その上製薬ほど幅広い化
学反応・技術を要するものはないので、化学工業の方面から着目され、多くの人がそちらで活
躍した。古いところで私の記憶にある人は古川政司(日本硫酸設立・水俣)、馬越幸治郎(ア
サヒビール創設)等で、私の友人もこの方面で研究所長や工場長を勤めた人が多いが、その
中で二、三を紹介する。同級の下里錠次君は大学で研究していたが、一つの仕事がまとまる
と先生の引き止めるのも聞かず、ブリヂストンに入り合成ゴムの研究を始めた。その揚句、ク
ロロプレーンの工場を作りあげた。原料が爆発するので苦労したが、日本の合成ゴム製造の
道を開いた。また私の二年下級の丸山正武君は軍人になったが、軍医学校でドイツの文献を
頼りにイオン交換樹脂の研究をした。戦後これを製造するオルガノという会社を作り、すっか
り財をなして、それを他の会社に譲り、自分は銀座に彩壷堂という美術の店をもち、悠々たる
一生を過ごした。この丸山君にはエピソードがある。彼の研究は海水を真水にする目的で行
なわれた。そのため携帯用の濾水器を作り、東條陸軍大臣の前で、兵士に海水を採らせ実
験して見せた。大臣は大変感心して丸山君に陸軍大臣賞を与えた。このデモンストレーション
にはからくりがあって最初から真水を入れておいた。失敗を恐れてのことだが、彼を知る者だ
けがありうると考える彼の博奕であった。
東大を卒業
徴兵、ソ満国境僻地の小病院へ
話は遡るが、私は大学を卒業すると、直ちに徴兵に会い、終戦まで八年間も軍務に服し
た。その間、ノモンハン事件の直後、ウラジオストックに近いソ満国境の僻地の小病院にやら
れた。ここで今まで経験しないことに出合ったが、その中に病院の氷の問題があった。私には
宿舎があったが、その風呂で体に湯をかけると流れる一方からチリチリと凍ってしまうのに、
この地の寒冷を目で見る思いがした。こんな土地(零下二十五度位になる)だから冬には自然
の氷が幾らでもある。しかし製氷器もない、地下に貯氷庫はあってもコンクリート壁から水がし
み出して氷が溶けてしまうとなると、夏場の氷は大問題である。私もいろいろと試行したが、そ
の結果、地表に氷を積み、おが屑をかけ、その上を莚で覆うことで何とか夏場までもたせた。
この作業の中で私は氷は、勿論程度が問題だが、熱より水に弱いことを知った。かくして一年
が過ぎようとした頃、思いもかけず、東京の陸軍衛生材料本廠研究部への転任の通知が舞
い込んだ。
東京の陸軍衛生材料本廠研究部
軍の組織を知らない人には解かり難いが、現役軍人でない者が一度関東軍(満州)に編入さ
れると他に移ることはありえぬことで、こういうことになった裏には私の想像しなかった動きと
事情があった。もしこれがなければ今の自分は存在したかどうかわからない。
ここでの初仕事は中国で押収した阿片の中のコカインの量を調べてくれということであった。コ
カインはコカのアルカロイドだから入っている筈はないと言ったら「君は若い」とやられた。阿片
を増量するためにコカインを混入するのである。次の仕事は寒冷地に送るアンプルが割れて
しまうから何か考えろという問題であった。それを防ぐには限定量のエチレングリコールを加
えるのであるがそれが利かない。薬品で代わるものを考えたが何も出てこないので東芝の研
究所と相談してアンプルを球形にすることで問題を解決した。これは薬に頼りがちな薬学の者
にとってよい教訓であった。
こんな細々した仕事の外、私に対する主な要望は中枢神経興奮剤(今の覚醒剤)の合成とマ
ラリア対策であった。当時、覚醒剤はエフェドリンから導かれたものが公然と薬局で売られて
いた。私はベンツェドリンという合成薬の別の製法の特許(権者は陸軍大臣東條英機になる)
をえて補給用としてある会社に作らせたが、この薬は作用後、反作用を伴うことがわかったの
で、補給を中止した。丁度この頃東條大臣の査察があって研究部へやって来て「米軍やソ聯
軍の飛行士はこういうものを用いているが当方はどうじゃ」と質問した。「そんな薬品はずっと
以前から補給しています」と廠長が答えたが、実情は既述のようであった。
抗マラリア剤の開発研究
マラリアの問題は南方戦線において戦わずして兵力を損耗させるから重大であった。マラリ
アはアノフェレスという蚊によって媒介される。この蚊のぼうふらは家蚊のそれが頭を水面下
に下げて泳ぐのに対し、体を水面に平行にして泳ぐ、従って殺虫剤の粉末を水面に撒いてや
ればそれを食べる。私はフェノチアチンがそれに有効なことを知り、ある会社に作らせた。こ
れはデイフェニルアミンと硫黄を溶融すると簡単に出来る。本来黄色の化合物であるが、下手
に作ると緑色を帯びる。ぼうふらは緑色のものを好むからこの方がよい。下手も芸のうちであ
る。南方の広範な地域にこれがどの程度効果があったかは疑問であったが要求は多かった。
マラリアの原虫は人の体内に入ると複雑なサイクルによって変態を繰り返す。しかもそのステ
ージによって利く薬が違うから始末が悪い。従来キノリン系とアクリジン系の化合物が用いら
れてきたが十分な対応は不可能であった。その上原料も不足勝ちになってきたので薬学の主
な先生を動員し、私も加わって戦時研究が行なわれた。結果としては既知の化合物に少し手
を加えた位で終った。私はスルホンアミドのある種のものがマラリアに効果のあることを知って
いたので、それとキニーネとの分子化合物を作った。それによってキニーネの苦味を無くすこ
とができたが、どの程度相乗効果があったのか、どの段階で利くのか不明のまま終った。戦
後この方面の研究の蓋が開けられたが、アメリカでは新規なグアニジン系化合物が開発され
ていた。ここでもアメリカに水をあけられた。
戦争も末期、日本製の碧素(ペニシリン)は効いたのか?
戦争も末期になり空襲も激しさを増す頃、目黒に工場をもつ万有製薬の社長から疎開工場
の紹介を緊急のこととして頼まれた。それで私は岡崎の実家にその所有する工場の一部を貸
すよう頼んでやった(これが今のメルク万有→万有の工場である)。ここには養蚕の研究のた
め温度を調節する施設があった。これを利用して梅沢博士が碧素(ペニシリン)を作った。我
が国でもペニシリンが出来たと大騒ぎをしたが、実情はどうかと言うと、ルー瓶を並べてペニシ
リウムを培養し、それをシャンベランで濾過して出来上がりとした程度のものであった。しかも
経口的に用いられたので果たして期するような効果があったかは疑問であるが、ひっぱりだこ
で取り引きされた。戦後アメリカは製造のノーハウと機器をいちはやく日本に与え、二十噸を
越す培養による大量生産が始った。量的のことばかりではなく、冷凍乾燥とか連続抽出装置
(エジェクター)のような新技術が含まれているのに驚いた。私は戦争中アメリカの化学特許を
調べたが、ただ「ビタミンAの分子蒸溜」位が目についた位でほとんど利用したいようなものは
なかった。ところが戦争が終ってみるとマラリア剤といいペニシリンの製造といい著しい発展を
とげていた。アメリカはいざとなると驚くべき底力を発揮することを改めて悟った。敗戦、東大
の研究室に戻る
再び東大の研究室で
戦争も終ってわれわれのドタバタの時代が始った。私も出直しのため大学の研究室に戻っ
たが、電気も、ガスも、水もとぎれとぎれに、しかも短時間より出ない。そのためミクロ合成と
称して少しで研究を捗らせようとしたが、うまくいく筈がない。ただそんな中で化学上思わぬ現
象に出会い、将来研究を進める方向を見付けたのは意外な収穫であった。しかしこんな環境
が続けば段々意欲も落ち込むばかりなので、何かによって賦活を計らねばならぬと考え、わ
れわれは薬学懇話会なるものを作り講演会などを開くことにした。そしてその資金は出版によ
って購った(季刊薬学なる総説誌などの発行)。最初の講演者には台北より引き上げられた
野副鉄男先生を選んだ。意外のことにこの先生はあのトロポロン(ヒノキチオール)の仕事を
殆ど公表していなかった。従ってこの講演が初公開になるので私は多くの人を聴衆に誘った。
農学部の後藤格次先生なども来てもらった。この先生は最前列に陣取ったが、講演が始ると
暫くして鼾をかき出した。私も驚きもし困りもしたが、講演が終るちょっと前にふと目を覚まして
質問に立ったのには更に驚いた。さすが唯者ではないなと感心した。
下山事件 − 謀略? 国鉄総裁謎の死
この頃下山事件という大事件が起きた。国鉄の下山総裁が出先から消え、死体が線路上
で轢断されて発見されたという事件である。そしてその死因が殺された後轢断されたものか、
自殺によるものか、その説が分かれた。東大法医学の古畑教授は他殺説をとり、薬学の秋
谷教授、塚元助教授は死体の乳酸値からそれを支持したが、慶応グループは自殺説をとっ
た。しかし結局結末がつかぬままに時が過ぎた。ところが最近「下山事件はまだ終っていな
い」という本を書いた人がいる。
*著者は当時熱心に密着取材した新聞記者の人ではないかと思うがはっきりしないし、どうい
うことが書いてあるかも読んでいないので知らない。
*<よか薬会注>
森 達也「下山事件」、新潮社 2004年2月。 なお塚元助教授とは後に九大医学部薬学科(後
の薬学部)の旧衛生裁判化学教室(第2講座)に教授として赴任された塚元久雄先生(物故)
のことである。
あとがき
終戦直後、ロージャー・アダムス博士を団長とする科学調査団が日本へやって来た。その時
博士は薬学科でも講演し、「日本の薬学はアメリカより良い」と言った。この調査団は日本に
サジェスチョンを与える目的もあったとので意外であったが、先生は学者らしく率直にその意
見を述べたのであろう。しかし私は言われたように良いとも思わないし、悪いとも思わない。大
体その存立が違った基本理念によって培われてきたからである。余談であるが先生は大麻の
成分カンナビノールの研究で有名であるが、化学戦争と言われた第一次大戦の時に、アダム
サイトという催涙ガスも作っている。私はあることから先生の知遇をえたが、アメリカでは人間
的に最も尊敬を受けた化学者である。こういう人まで巻き込むのが戦争である。
私は前書きで述べたような主旨で思い出すままのことを書いてきた。唯単純に昔はこんなこと
もあったということを伝えておきたいという本能的な気持と幾らかの悪い茶目気からであって、
これが何等かの意図をもつものでもないし、今後に影響を与えることを望んでいるのでもな
い。昔は昔、今は今である。要するに私というじじのおしゃべりの一つと思って頂きたい、それ
だけのことである。
(ここに書いたことは私が九大へ来た昭和26年以前の話である。来てからのことはまだ生々
しいし、話の種がなくなることにもなるので後にとっておく。)
よか薬会付記
毎年11月(第2土曜日 夕刻)、よか薬会(九州大学薬友会福岡支部)の総会・講演会・懇親
会を開催している。懇親会では参加された方々にご挨拶やお話しをいただく。その中で田口
先生による薬学の回顧談はすっかりこの会の恒例行事となった。先生のお話を聞くのが楽し
みでこの会に参加する同窓生もいるくらいである。近代の体系的学問としてまず東京大学に
始まった日本の薬学の、いわゆる正史にはけっして現れてこない興味深いエピソードが、先生
の巧みな語り口によって眼前に彷彿としてくる、毎回お聴きするだけではなんとも勿体ない、そ
ういうお話しである。そこでよか薬会役員会は記録として残すべきであると考え、田口先生に
あらためてご無理を申し上げ『私を通しての薬学の裏話』としてまとめていただいた。タイトル
の趣旨は先生の「まえがき」にあるとおりである。
ところで昭和25年(1950年)4月に、旧帝大系では東大、京大についで全国3番目の薬学と
して九大医学部薬学科が発足した。田口先生はその翌年の昭和26年(1051年)に九大に
教授としてご赴任になり、昭和51年(1976年)のご退官まで薬品製造化学教室を主宰して研
究・教育および薬学部[昭和38年(1963年)までは医学部薬学科]の運営に当たられた。今
回田口先生がお書きになった『私を通しての薬学の裏話』は、九大ご赴任以前のものである。
しかし私たち九大の卒業生としては、九大時代の『裏話』が聞きたいと思うのはやはり当然だ
ろう。そこで、「ここに書いたことは私が九大へ来た昭和26年以前の話である。来てからのこ
とはまだ生々しいし、話の種がなくなることにもなるので後にとっておく。」(「あとがき」)として
渋っておられる先生に再びご無理を申し上げた。さいわいこの冬にお書きくださるとのことであ
る。『私を通しての薬学の裏話−プレ九大時代』としたのはそういう理由である。『私を通して
の薬学の裏話−九大時代』(仮題)はいずれ薬友会誌上でお目にかかることができるはずで
ある。
田口先生には今後ご夫人ともどもますますお元気にお過ごしになり、次回の2005年よか薬
会総会・講演会・懇親会でまたすてきなお話しを私たちに披露して下さることを心より願ってい
る次第である。
なお、今回秋山聖五郎氏(13回生、S39年卒)にはよか薬会役員ではないにもかかわらず、
田口先生との連絡係をこころよくつとめていただいた。厚く御礼申し上げる。ちなみに秋山氏
はさる水彩画教室の3年生で20数年生の田口先生と同級生である。
(文責 野田浩司 2004年11月下旬)
|
 よか薬会のトップページへ プレ九大時代のトップへ
よか薬会のトップページへ プレ九大時代のトップへ